今の職場に悩んでいたら・・・

\ 簡単10秒登録 /


\ 簡単10秒登録 /

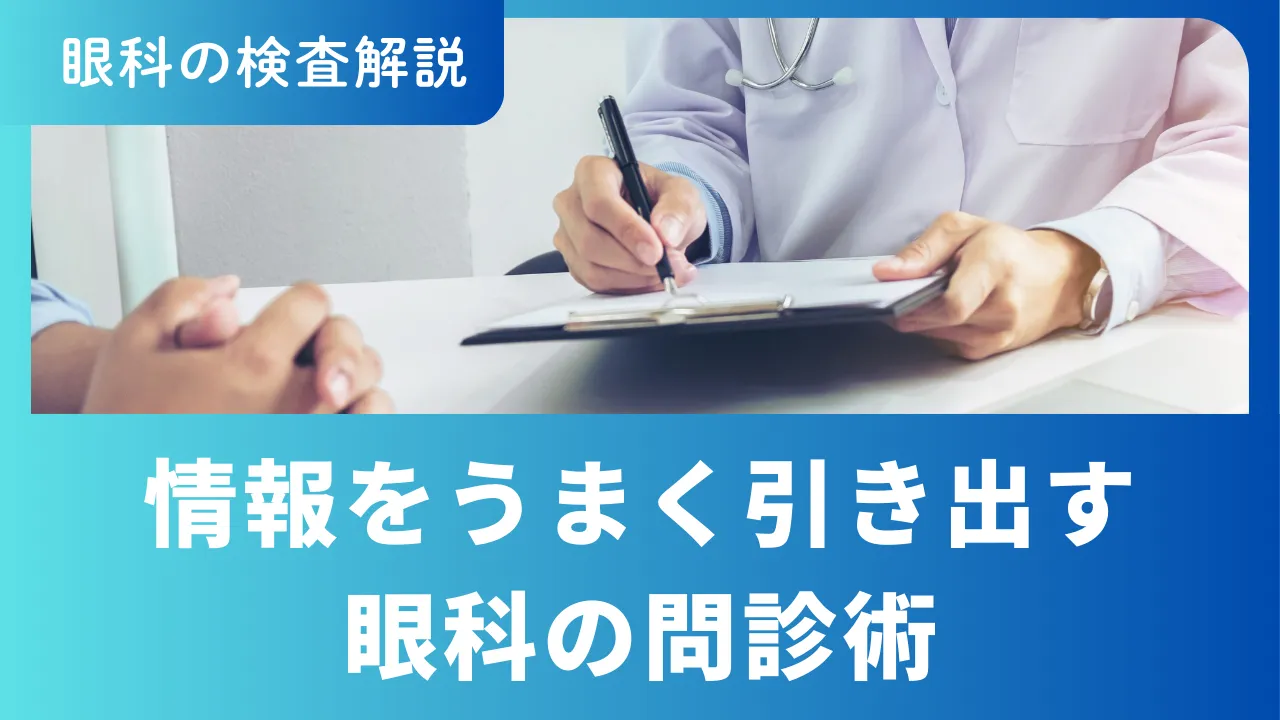
検査時に患者さんをお呼びして、
まず最初に行うのが問診です。
臨地実習中や入職したばかりの
新人が任されることも多いでしょう。
問診は、検査や診察をスムーズに
行うためにとても重要な項目です。
この記事では、問診において検査や
診察に必要な情報をうまく引き出す
ためのポイントを解説します。
問診の段階で必要な情報を聞き出せ
れば、検査や診察の効率化につなが
ります。
問診が不十分だと必要のない検査を
したり、診察に時間がかかったりと
正しい診断結果が出るまでに遠回り
してしまう可能性があります。
また、問診から得られた情報で検査の
方向性や注意すべきポイントが把握
できることも多く、視能訓練士が
検査を行う上でも役立ちます。
問診では、緊急性があるかどうかも
常に意識し、早急な診察や処置が
必要なケースを見抜くことが重要です。
具体的には以下のような症状や疾患
が挙げられます。
緊急度の高い眼科疾患
緊急性があると考えられる症状
急激な視力低下に加えて「視界に
カーテンのような膜がかかって見える」
といった訴えがある場合は、網膜剥離
の可能性も考えられます。
流行性角結膜炎(EKC)が疑われる
場合は院内感染を防ぐため、検査を
行わず診察に回す必要があります。
確認したいポイントは以下の3点です。
「充血」「めやに」「かゆみ」などの
訴えがある場合は、EKCの可能性も
考えながら問診を進めましょう。
問診では、患者さんの訴えをそのまま
聞き流せばよいわけではありません。
話を聞きながら要点をまとめ、詳しく
確認すべき点に対しては、こちらから
質問することも必要です。
問診を取りながら、患者さんと一緒に訴えを整理していくイメージで行ないます。
患者さんとのコミュニケーションは、
問診や検査をスムーズに行うために
とても大切です。
しかし時には「問診をしていたはずが、
気付いたら患者さんと世間話になっていた」
ということもあります。
 先輩視能訓練士
先輩視能訓練士話が逸れていることに気付いたら軌道修正し、流されないように意識しましょう


初診では問診票をもとに患者さんの話を
聞いていきます。
主訴が多い場合は「最も困っている症状は
どれか?」と確認し、受診した理由や優先
順位を明確にしましょう。
「特に困っているわけではないが当てはまる
症状には丸をつける」という患者さんも
少なくありません。
初診の問診では目の症状に加えて以下の
ようなことも確認し、患者さんの情報を
集めます。
「見えにくい」訴えがある場合は
散瞳の可能性も考慮し、交通手段も
確認しておきましょう。
例)初診の60代女性「急に見えにくくなった」
・「急に」とは具体的にいつ?
数時間前?数日前?数か月前?
→ 緊急性の有無を確認
・どのような見えにくさ?
→ かすむ、ぼやける、真っ暗になるなど
・見えにくいのは右目?左目?両目?
・見えにくいのは遠方?近方?
・眼鏡は装用している?
→ 装用している場合:眼鏡をかければ見える?
※見えにくい=「眼鏡をかければ見えるが、
裸眼だと見えにくい」という場合もある
・来院時の交通手段は?
→ 主訴から散瞳の可能性が考えられるため


再診の問診は「変わりない」の一言で
終わることも多いですが、患者さんから
の訴えや情報を聞き流さないように注意
します。
特に、眼鏡処方や手術、レーザー後の問診は
丁寧に行なって下さい。
問診の「聞き方」も大切です。
「変わりないですか?」
だけではなく、
「前回は〇月に来院されていますが、その後目のことで変わった点や気になる点はありましたか?」
という聞き方をすることで、患者さん
も前回受診時以降のことをイメージ
しやすくなります。
また、問診時には特に訴えがなかったと
しても、その後の視力検査で前回値よりも
明らかな視力低下が認められる場合は、
再度見え方について確認して下さい。
例)50代男性
「前回、初めて近用眼鏡を処方した」
・眼鏡は作成したか?
→ 作成していない場合:
その理由は?作成する意思はあるか?
・本日は作成した眼鏡を持参しているか?
→ 処方通りか度数を確認
・作成した眼鏡を使用しているか?
→使用していない場合:
その理由は?装用感?見えにくい?
→使用している場合:
装用感はどうか?気になることはないか?
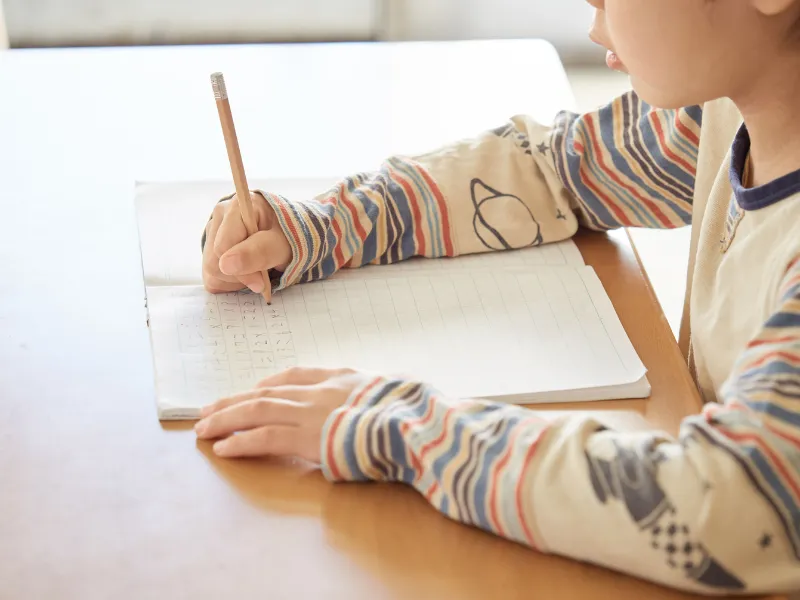
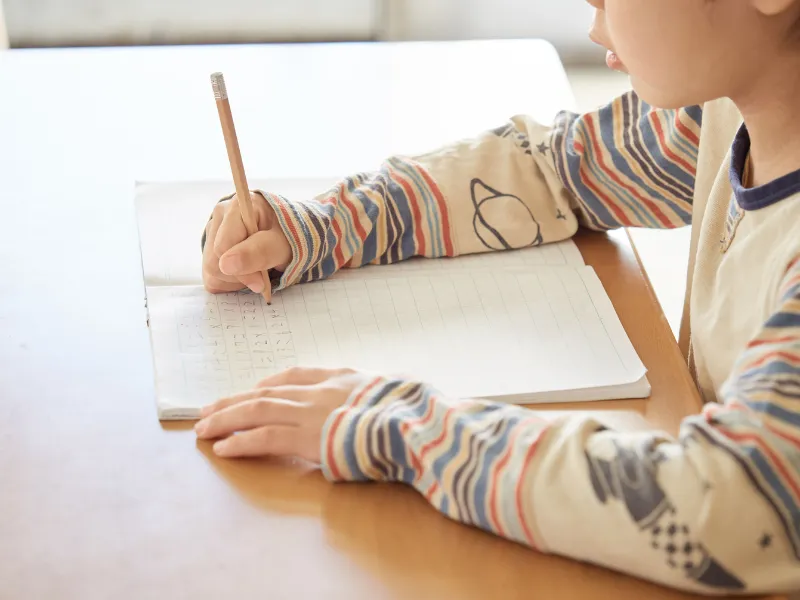
小児の問診は基本的に保護者に対して
行なうことが多いですが、受け答えが
可能な年齢であれば本人に対しても
行います。
その場合は必ず保護者からも普段の
様子を聞き出し、本人の訴えと照らし
合わせましょう。
心因性視力障害が疑われる場合は、
本人と保護者への問診を同じ場所で
行わないよう配慮してください。
例)小学2年生の女児
「学校健診で両目ともC判定だった」
(本人に対して)
(保護者に対して)
患者さんをお呼びして一番最初に行なう
問診は、眼科検査や診察の基本です。
情報をうまく引き出せれば、その後の
検査や診察が効率的に行なえるため、
結果的に患者さんの負担も軽減できます。
問診の聞き出し方や言葉選びによっても、
患者さんから得られる情報量は変わって
きます。
患者さんの気持ちに寄り添って、
と振り返りながら問診術を高めていきましょう。


\ 簡単10秒登録 /

