今の職場に悩んでいたら・・・

\ 簡単10秒登録 /


\ 簡単10秒登録 /


 視能訓練士
視能訓練士OCTって簡単に撮れるときとすごい時間かかるときがある…
OCT(光干渉断層計)検査について
「固視が良くて撮りやすい患者さんなら
問題なく撮影できるけど、少しでも
問題があると手間取ってしまう」
という人もいるかもしれません。
難易度の高い患者さんの測定時間を
短縮できるよう、参考にして下さい。
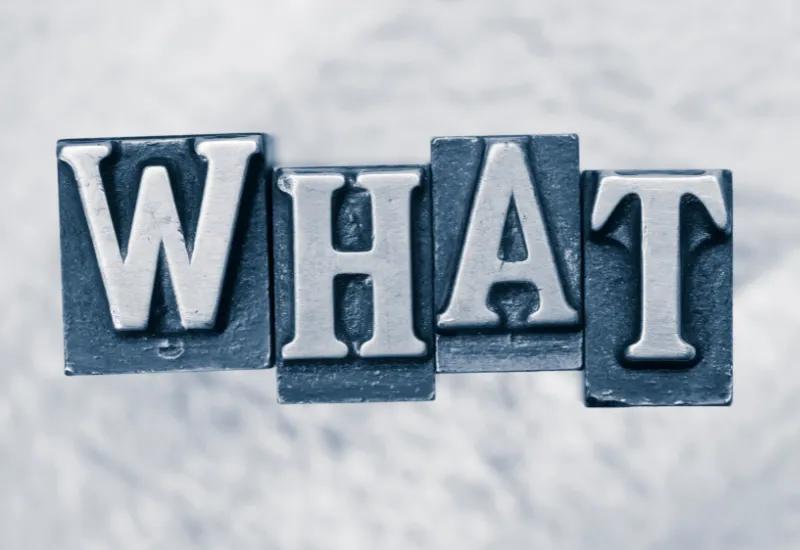
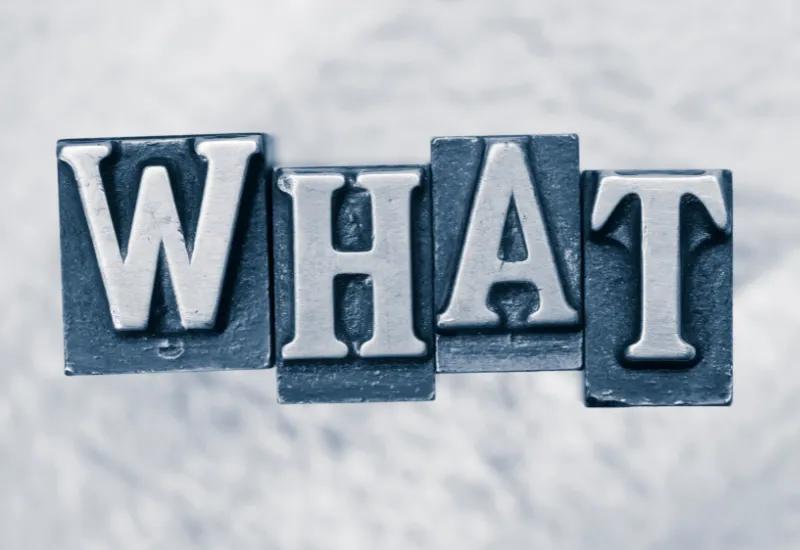
「目の奥に網膜という膜があるの
ですが、その断面の写真を撮影
する検査です」
眼底写真とOCTの違いを聞かれる
こともあります。
「眼底写真は眼の奥の写真、
こちら(OCT)はMRIのように
目の奥の断層像を撮影します」



上記のような説明をすれば深く突っ込んでくることは少なく、たいていの方は納得されます


OCT検査をスムーズに行うために、
ベテランが意識しているコツを解説
します。
検査に慣れてきたり、忙しかったりすると
流れ作業のようにOCT撮影を行いがちです。
しかし、撮影中は必ず声かけをして、
無言で撮影することは避けて下さい。
以下のようなこまめな声かけは、
患者さんに丁寧な印象を与えるだけ
でなく、固視を安定させてスムーズに
撮影できるというメリットもあります。
【眼瞼挙上時】
【撮影時】
【解析中】
OCT撮影時は、基本的にほぼすべての
患者さんに対して眼瞼挙上して下さい。
器械によっては撮影時にまぶしさを
感じるものもあり、挙上した方が
より確実に眼瞼の影響を受けず、
鮮明な画像を撮影できるためです。
ずっと挙上したままだと患者さんが
瞬きできないため、適度に挙上を
緩めながら声かけで瞬きを促す
など配慮して下さい。



瞬きできないと患者さんは苦痛です。気をつけましょう
など、あらかじめ撮影に時間がかかることが予想される場合は、
「今日はいつもより多めに撮影するので、少しお時間がかかります」
などとあらかじめ患者さんに
伝えておいて下さい。



何も知らされないまま、撮影に時間がかかると「なにか異常があるのでは」と患者さんが不安に感じてしまいます
※1時~12時まで、時計に見立てて眼球のどこに疾患があるかを示した呼び方です
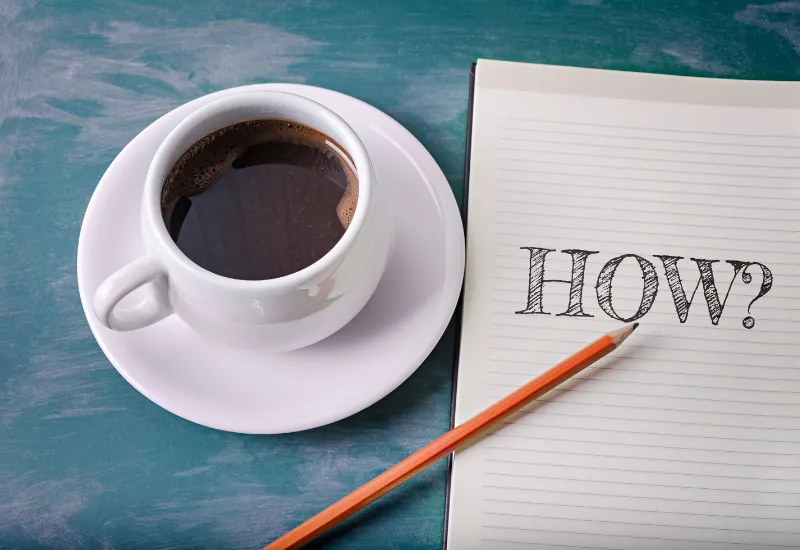
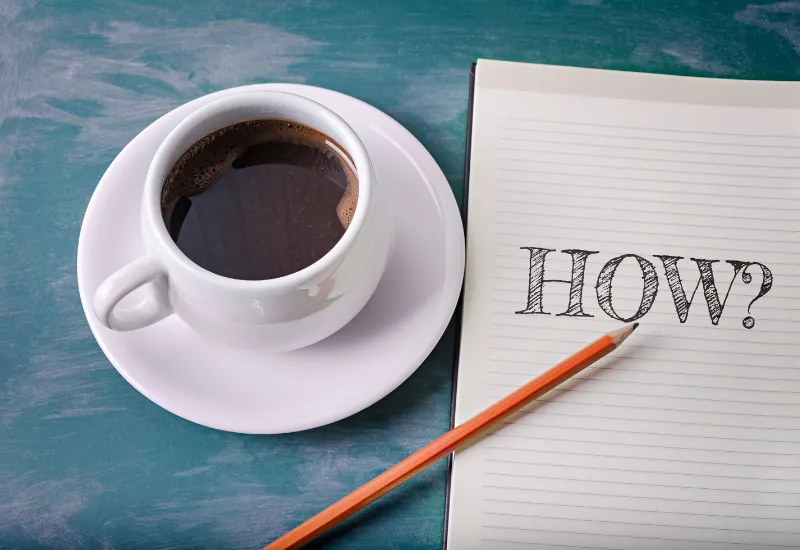
OCT検査で対応に困りがちな場面と、
その対処法について解説します。
OCTには内部固視灯がありますが、
低視力のために見えない患者さんも
多いです。
その場合は以下のように、声かけで
固視の誘導を行なって下さい。
【黄斑部】
「まっすぐだと思う場所を
見ていてください」
【disc(視神経乳頭)】
「少しだけ右(左)側を
見てください」
もし片眼の視力が良好であれば、
OCTの外部固視灯やペンライトなど
を使うと固視誘導の微調整が
しやすくなります。
「discをもう少し中心に位置させたいから、もう少し〇側を見てもらう」
など、患者さんが目を動かす方向と
眼底像の関係がすぐにわかるように
しておくと、OCTや眼底写真撮影の
際にはとても役立ちます。
視力的には内部固視灯が見える
はずなのに「見えない」と訴える
患者さんもいます。
その場合は
「赤/緑色のバツ印が見えますか?」
など固視灯の特徴を伝えて下さい。
disc撮影時は正面から左右の少し
ずれた位置に固視灯が出るため
「少し右(左)側に見えませんか?」
と声かけします。



それでも固視灯が見えない場合は、速やかに声かけや外部固視灯などで誘導する方法に切り替えて下さい
白内障が進行していると、水晶体の
混濁が妨げになって網膜像が鮮明に
描出されません。
その場合は瞳孔の中心から少し位置を
ずらしながら、混濁が少ない部分
(網膜像が少しでも鮮明に見える場所)
を探すように撮影して下さい。
この方法は眼底カメラ撮影時にも
使えます。
どの場所でも混濁が強い場合は
「混濁が強く、これ以上は撮影できず」
とカルテに記載して下さい。
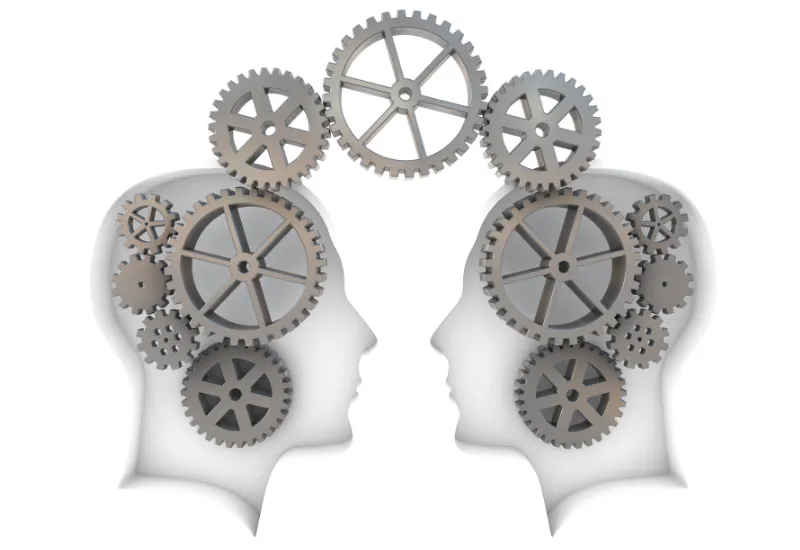
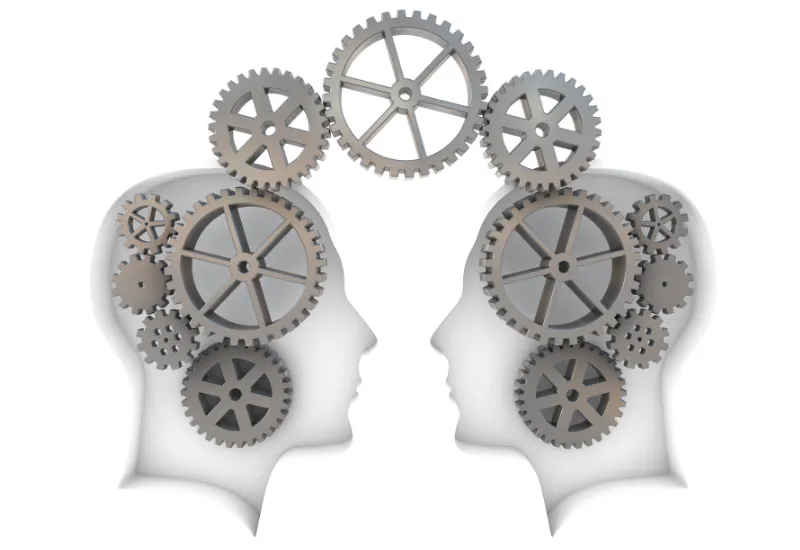
OCTの撮影が難しい場合に、
どこまで粘るべきかの判断例を紹介します。
など撮影が困難な場合は、
かろうじて黄斑部分が測定できればOK
とし、検査状態や測定困難である
理由をカルテに記載しましょう。
【カルテへの記載例】
「姿勢の保持が難しいため、
これ以上は撮影できず」
硝子体出血や硝子体手術後の
患者さんは、鮮明な網膜像が
得られにくく撮影が困難です。
可能であれば先に眼底写真を撮影
しておくと、OCTが撮影できそうか
どうかの判断材料になることも
あります。
撮影が難しい場合は、カルテに
「これ以上は撮影できず」
と記載して下さい。
特に硝子体手術から間もない場合、
傷口や患者さんの負担を考えると
あまり時間をかけるべきでは
ありません。



自信がなければ、自分よりも経験のあるスタッフに代わってもらって下さい


OCT検査時の失敗談と、その経験から
得た注意ポイントを紹介します。
なかなか画像が描出されず、
おかしいと思ったら無水晶体眼の
患者さんだった!
【注意ポイント】
OCT本体のID変更を忘れ、
誤って前の患者さんのIDで撮影
してしまった!
【注意ポイント】
凡ミスではあるが、忙しいときなどにやってしまいがち
修正対応には時間がかかり、
万が一ミスに気付けなかった場合は
診察で大きな問題になりかねない
OCTで撮影困難な症例に対応できるか
どうかは、これまでの撮影経験も
大きく影響します。
まずは基本的な手技や撮影のコツを
おさえて、さまざまな症例のOCTを
撮影して下さい。
失敗から学べることも多いため、
たとえうまくいかなくても次回に
活かしましょう。



失敗は多いけど、確かにその分学べることも多いです



症例数をこなして、試行錯誤を繰り返すことが上達への近道です!


\ 簡単10秒登録 /

