今の職場に悩んでいたら・・・

\ 簡単10秒登録 /


\ 簡単10秒登録 /

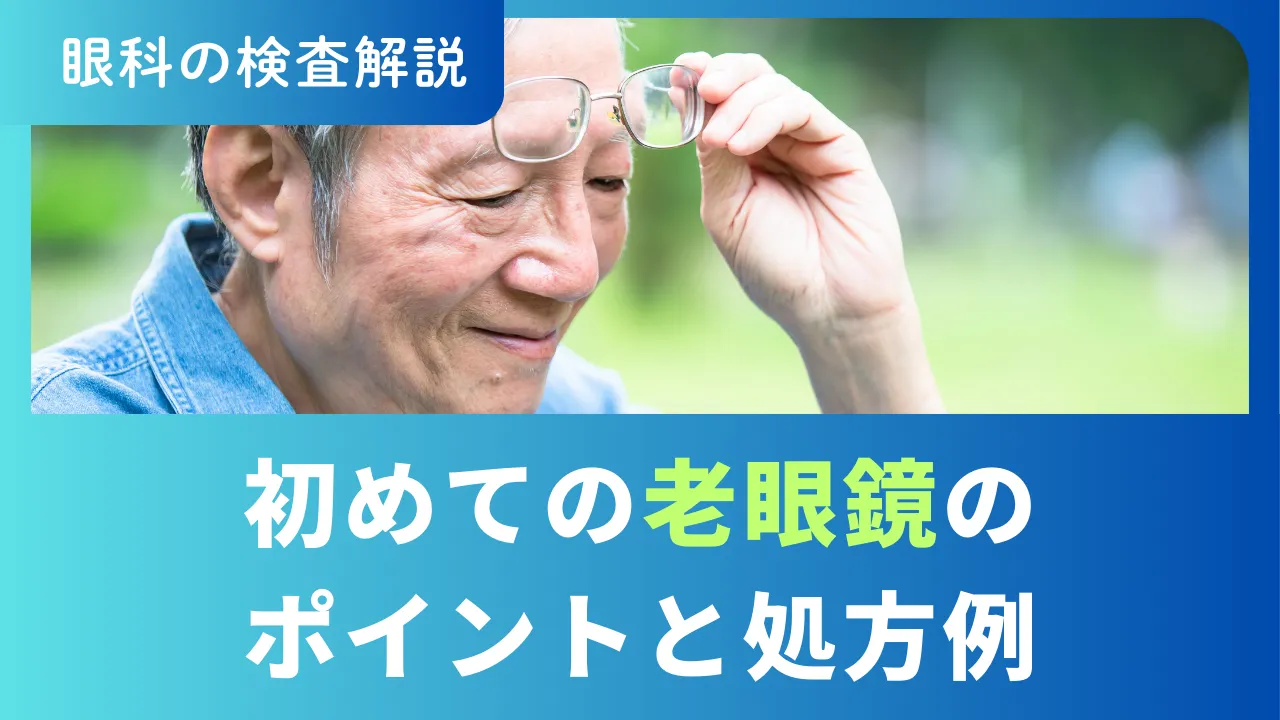
老眼鏡(近用眼鏡)処方では、
視距離の聞き取りがとても重要
です。
「どんなものをどれくらいの距離
で見たいか」を具体的に把握し、
患者さんが日常で眼鏡を使用する
状況をイメージしながら処方する
ことが、満足度に繋がります。
今回は、40~50代で初めて老眼鏡
処方となった場合の眼鏡処方を、
具体的な処方の手順や患者さんへの
説明、注意点などを解説します。

近用単焦点(老眼鏡)の処方に
向いているのは次のような方です。
累進眼鏡の処方についてはこちらの
記事を参考にして下さい。
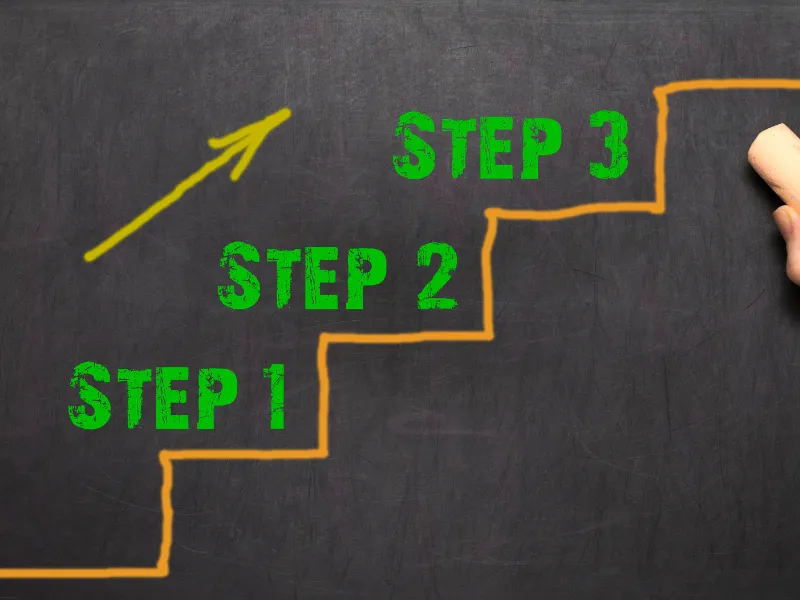
まずは、老眼鏡処方の手順について
解説します。
処方に必要な情報は以下の2点です。
①②の情報をもとに度数の選定を
していきます。
問診では、患者さんのニーズを
しっかりと把握し、患者さんが
日常で老眼鏡を使う場面を具体的に
イメージすることが重要です。
などを確認し、深堀りしていきます。
問診で深掘りする具体例
新聞
パソコン(PC)
 先輩視能訓練士
先輩視能訓練士近用単焦点はとにかく距離が大事なので、対象物の使用状況を細かく聞き取ります!
近見作業の状況を患者さんに再現してもらい、実際の視距離をメジャーで測定
して下さい。
何もない状態で再現するのは難しい
ため、近用眼鏡処方用として新聞や
雑誌などを検査室に常備しておくと
便利です。
例えば、
などの場合は、可能であれば検査室の
にあるデスクに座ってもらったり、
院内のパソコンを使って確認したり
するとより確実な視距離が把握できます。
院内のパソコンをサンプルで使う場合は、個人情報のわかるページをすべて閉じて下さい!
視距離×年齢=近用度数のベース決定
視距離と患者さんの年齢をもとに
必要調節力を計算し、度数を決定
します。
必要調節力はあくまでも目安のため、
実際に装用してもらい反応を見ながら
微調整してて下さい。
年齢と距離ごとの必要調節力(目安)
| 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | |
| 30cm | +2.00D | +2.25D | +2.50D | +2.75D | +3.00D |
| 40cm | +1.50D | +1.75D | +2.00D | +2.25D | +2.50D |
| 50cm | +1.00D | +1.25D | +1.50D | +1.75D | +2.00D |
※上記表は弊社スタッフの所属施設で、実際に使用しているものです。
一部「教科書と異なる」かもしれませんが、この表はあくまで目安です。
この表の数値をもとに、度数を増減させて患者さんの自覚的ベストな数値を探します。



必要調節力は個人差があるため、あくまで一つの手がかりとして下さい
度数決定の具体例
| 50歳男性 | |
| 視距離 | 45cm(新聞) |
| 年齢の必要調節力 | +1.75D (上記表より類推) |
| 完全屈折矯正値 | R (1.2✕+1.00D) L (1.2✕+1.00D) |
| 眼鏡処方値 | R +2.50D L +2.50D |
(このとき、45cmの距離で新聞を見てもらう)
(+1.00D)+(+1.75D)
R +2.75D
L +2.75D
ステップ①に±0.25Dをそれぞれ重ねて、自覚を聞く
R +2.50D~+3.00D
L +2.50D~+3.00D
患者さん本人の自覚で、
を選んでもらう
初めて老眼鏡を作製する患者さん
は、眼鏡自体が初めての場合も
多いため、
をしっかりと説明して下さい。



説明や理解が不十分だと「遠くが見えないと訴える」「テストレンズを装用したまま歩き回る」など、本来のテストができないことがあります
装用テストの説明例
この度数で違和感や疲労感などがないかどうか、実際に少し長い時間かけてもらって確認します。
この眼鏡(検眼枠)には手元用の度数が入っているので、遠くを見るとぼやけます。
「クラクラする」など少しでも気になることがあれば教えて下さい。


初めての老眼鏡処方では、患者さん
への基本的な説明も重要です。
老眼に関する認識があいまいな患者さん
も多く、中には「自分が老眼である」
ということに対して、ネガティブな感情
を抱く方も少なくありません。
患者さんの性格を理解した上で、
場合によっては
「老眼」という言葉を言い換えて慎重に説明する
など配慮して下さい。
配慮した説明のポイント
年齢を重ねると、目のピント合わせの筋肉が疲れやすくなり、思うように働かなくなってしまう。
手元を見るときはピント合わせが必要なので、ぼやけたり見づらくなったりする。
そのままの状態だと見づらいだけでなく目も疲れてしまうので、手元用の眼鏡をかけてピント合わせを助けてあげる必要がある。
※「老眼」という言葉を使わない



老眼鏡をかけると老眼が進行する、というのも誤りであることを伝えて下さい
「友人に勧められた」などの理由で、
累進レンズに興味を持っている
患者さんも少なくありません。
「累進=万能レンズ」と思い込んで
いる場合も多いため、累進の話が
出た際はデメリットも含めて
しっかりと説明して下さい。
説明例
遠近両用レンズは、一枚のレンズに遠くから近くまでの度数が入っている。
そのため、使い方にコツが必要で慣れるまでは少し難しく感じるかもしれない。
レンズの構造上、通常の眼鏡よりも違和感が出やすく、人によっては向かない人もいる。
また、遠近両用は基本的に常にかけっぱなしの眼鏡であり「見づらいときにかける」というものではない。
初めて眼鏡を作製する場合も多い
ため、技術や知識・アフターケアの
面で安心できる中価格帯以上の
眼鏡店を勧めます。
しかし、弱めの度数での作製や、
年齢的に今後も老眼が進行する場合
は、眼鏡の作り変えが必要である
ことを十分に説明して下さい。



レンズの保証期間についても触れ、期間が長い店舗での作製を案内しましょう
初めての老眼鏡処方では、視距離を
具体的に把握することに加え、
「老眼になってしまった」という
患者さんのネガティブな感情に
寄り添いながら検査を進めること
が大切です。
眼鏡処方では、検査中のコミュニ
ケーションや信頼関係が処方後の
満足度にも影響してきます。
患者さんの性格やタイプを理解し、
配慮しながら心理的な距離を縮めて
いきましょう。


\ 簡単10秒登録 /

