今の職場に悩んでいたら・・・

\ 簡単10秒登録 /


\ 簡単10秒登録 /

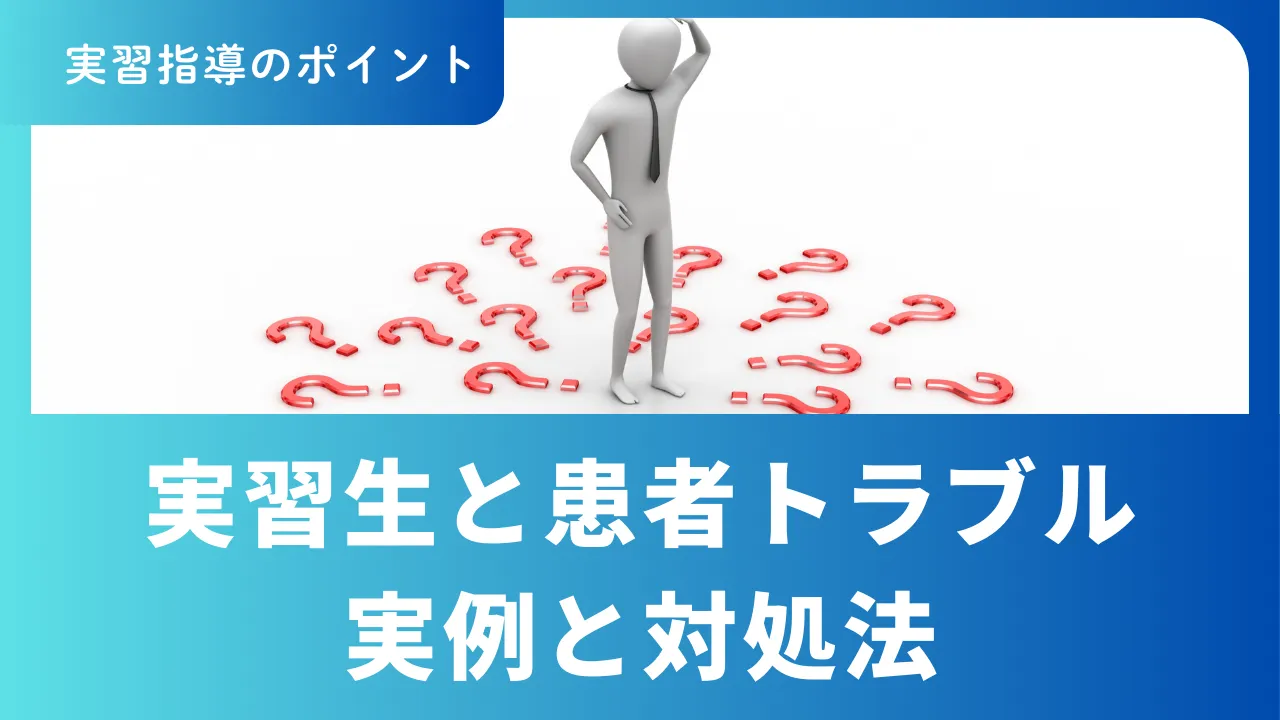
 視能訓練士
視能訓練士実習生に検査をさせたいと思うけど、患者さんとトラブルが起きたらどうしよう…上手に対処できるかな?
実習生を検査させたいけれど、患者さん
とのトラブルが起きないか怖くて、結局
見学ばかりになってしまうことはない
でしょうか?
トラブルが発生すると眼科施設への信頼
関係にも影響するため、指導者の責任は
重大です。
しかし、実習生への指導方法をきちん
と考えれば、実習生と患者さんの
トラブルをグッと減らすことができます。
今回は実際に起こったエピソードを
踏まえて、実習生と患者さんとの
トラブルとその対処法について紹介
します。



「実習生に積極的に検査をさせたい!」と思う指導者さんの参考になれば幸いです
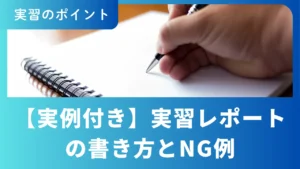
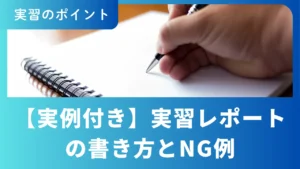


実習生と患者さんとのトラブルで
多いのは「患者さんの取り違え」です。
特に来院患者数の多いクリニックや、
患者さんの所在がわかりにくい大学
病院、総合病院では注意が必要です。
事例
暗室で指導者がOCT検査をしていた時、
実習生に「この患者さんを呼びこんで
きて」と指示を出しました。
実習生はすぐに呼び込みに行き、連れて
きた患者さんを席に案内しました。
しかし、
指導者が改めて本人確認をすると、違う患者さんであることが発覚
したのです。
患者さんには謝罪し、待合室に
戻ってもらいました。
実習生の話では、
「名前を呼んだら返事をされ、特に確認することもなくそのまま案内してしまった」
というものでした。
原因
その患者さんはご高齢の方で耳が遠く、
カルテにも「耳が遠い」と情報が記載
されていました。
実習生は難聴であるという情報を見落とし、
まさか「自分の名前を聞き間違えるわけが
ない」と思い込んでいたため、違う患者さん
をそのまま案内してしまったのです。



実習生は医療機関で起こりうるトラブルについて認識が甘いので、指導者自身が眼科で起こるミスを把握しておきましょう
眼科でよく起こるミスを把握しておく
と、実習生指導にも役に立ちます。
名前の聞き間違いによる患者さんの
取り違えだけでなく、点眼の左右を
間違えるなど、端から見れば「まさか」
のようなミスが、眼科では起こります。
というあってはならない話もあります。
思い込みや確認不足によるミスは、後々
大きな医療事故につながる可能性が高い
ため、普段から日常的に起こりうる
インシデントに注意を払って下さい。
指導者は「実習生はミスをするもの」
という前提で監督し、患者さんの取り
違えを”必ず”防ぐべく、本人確認を
徹底するよう指導しましょう。
など、必ず本人確認をするよう指導して
下さい。



ゆっくりでいいので、確認作業することを徹底させましょう


ある実習先で指導者が、
「今は実習中だからとりあえず教科書通りに視力を測って」
と実習生に指導していた際のトラブル
です。
事例
実習生は視力検査の途中経過をメモ
しながら必死で視力検査をしていました。
あるとき少し強面な男性の患者さんが
「眼に薬品が入った」という主訴で来院
され、指導者は実習生にその方の視力を
測るように指示をしました。
実習生は(びくびくしながら)その方の
視力を測っていましたが、あきらかに
検査速度が遅く、その患者さんから
「いつまでやってんだ!」とクレーム
を言われてしまったのです。
実習生はすぐに指導者に報告をして、
検査を代わってもらい、何とか事なき
を得ました。
原因
指導者が患者さんの性格や心理的状況
(痛みがありイライラしているなど)を
把握しきれていないまま、実習生に振って
しまったことが本事例の大きな要因です。
などがわからない患者さんを実習生に
任せないようにして下さい。
本事例のようなクレームが発生すると、
実習生の精神的な負担だけでなく、
患者さんの施設への信頼性にも影響
を及ぼします。
実習生には視力が出やすい、または
常連の患者さんで性格が穏やかな人
などが望ましいですね。



視力が安定しない、出にくい可能性がある、クセのありそうといった患者さんの検査は、実習生にはさせないほうが無難です
視力検査やGPを行なうときに、実習
では教科書通りのやり方で指導するの
ではなく、臨床に基づいた検査手技で
指導するようにして下さい。
教科書上の検査手技は重要ですが、
患者さんからすると、もたもたして
いるだけにしか感じられず、トラブル
発生のもとになる可能性が高いです。
実習では教科書上のことよりも、
患者さんとのコミュニケーションの
取り方を教えることを重視して下さい。



「教科書のやり方をベースにして、どう検査したらいいと思う?」と、実習生とディスカッションして、臨床のやり方と照らし合わせてもいいですね


これまで何度も視野検査を経験している
緑内障患者さんのHFAを実施した際の
トラブルです。
事例
実習生は小さい声で検査の説明をして、
検査中にほとんど声かけすることなく、
HFA検査を進めていました。
実習生が検査しているところを、指導者
は見えない場所で観察していました。
検査終了後、患者さんが
「ほんとにちゃんと検査をやってるの?そもそもなんで実習生が検査をしてるの?」
と実習生に少し怒った口調で問い詰めた
のです。
すぐに指導者が出て行って検査結果を
確認し、問題がない旨を説明したところ
納得してもらえました。
なぜ検査中に声かけしなかったのか
実習生に聞いてみると、
「検査が上手にできていたので必要ないかと思った」
という返答が返ってきました。
原因
患者さんへの配慮の不足
常連の患者さんでHFAもやり慣れて
いるから、実習生でも大丈夫だろうと
判断し、患者さんにその事実を伝えずに
実施してしまったことが原因の一つです。
そのほか、患者さんから見えない場所
での監督が、かえって患者さんの不安を
あおってしまった結果となりました。
慣れた患者さんであっても、
などをしっかりと伝えてから検査を
行ないましょう。
場所にもよりますが、患者さんから
見えるところに立ち、「ちゃんと
見ていてくれる」と安心してもらった
方が良いケースもあります。
患者さん側からすると、実習生に検査を
されるというのは不安なことです。
患者さんによっては「実習生は嫌」と
断る方もいるかもしれませんが、事前に
聞けばトラブルにはならないでしょう。



普段と違う状況になることをあらかじめ伝えるのは患者さんへの配慮です
HFAをする際は、たとえ検査が問題
なく進んでいなくても、
など、声かけをするように指導
しましょう。
自信がなさそうに検査の説明を
されたり、検査中に一切声かけが
なかったりすると、たとえ検査を
やりなれている患者さんでも、
「軽く扱われているんじゃないか?」
と不安になり、クレームトラブルに
発展することもあります。
気遣いのある声かけをすれば、たとえ
検者が実習生であっても、クレームに
発展する可能性は低いはずです。



検査中の声かけや患者さんとのコミュニケーションは検査結果にも影響が出るくらい大切なことです
実習生と患者さんとのトラブルと
対処法について、エピソードを
交えて紹介しました。
実習生と患者さんとのトラブルを
避けるには、
を重点的に指導しましょう。
もしトラブルが起こっても、
ただ厳しく指導するだけではなく、
しっかりフィードバックして、
「なぜトラブルに発展してしまったのか、どうすれば防げるのか?」
を考えさせるように指導して下さい。
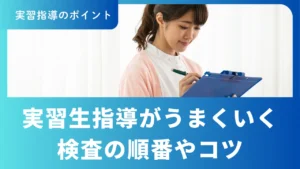
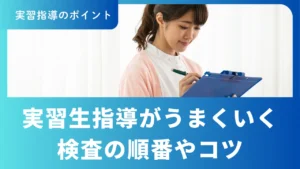


\ 簡単10秒登録 /

