今の職場に悩んでいたら・・・

\ 簡単10秒登録 /


\ 簡単10秒登録 /

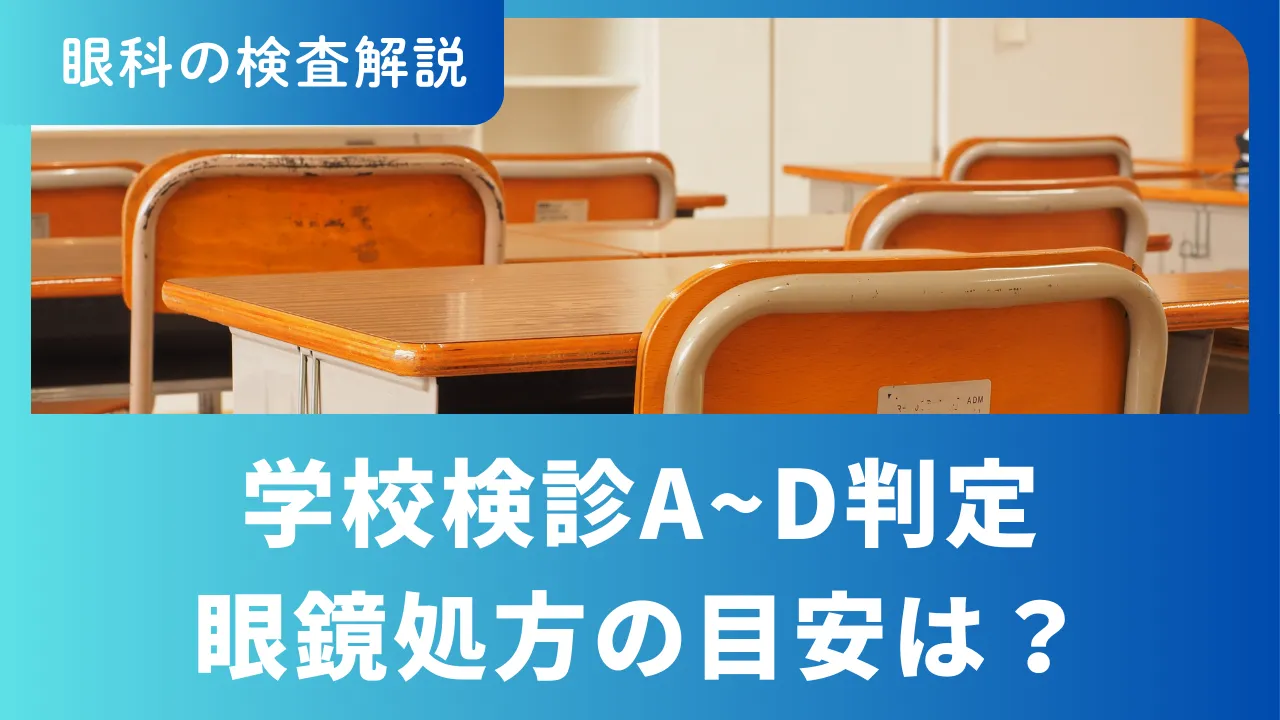
 視能訓練士
視能訓練士学校検診のA~D判定、眼鏡処方を勧めるべきなのはどこから?
毎年、学校検診の時期になると、
多くの小児が検診結果の紙を
持参して眼科を受診します。
検診のA~D判定は実際の検査結果
とは異なり、
どの結果であっても眼鏡処方の可能性があること
を理解した上で問診や検査を
行わなければなりません。
この記事では、学校検診で引っかかった
小児に対する検査の流れや注意点、
眼鏡処方を検討する視力の目安などを
解説します。


まずは、学校検診とはどのような
ものなのかを確認していきましょう。
学校検診では、視力の表記を
「A」「B」「C」「D」の
4つの記号で表記します。
それぞれの判定に該当する視力は以下の通りです。
A判定:視力1.0以上
B判定:視力0.7~0.9
C判定:視力0.3~0.6
D判定:視力0.2以下



これは全国共通ですよ!
A判定以外の場合は、
・近視、遠視、乱視
・その他眼に何らかの病気が隠れている可能性
があるため、保護者に
「受診勧告のお知らせ」が配布
され、眼科受診が勧められます。
検診結果であるA~D判定の信頼性は
あまり高くないため、あくまでも
目安として捉えて下さい。
理由として、
学校検診の目的はあくまでもスクリーニング
であり、検査を行なっているのも
視能訓練士や看護師等のような
眼科知識を持った者ではないためです。
視力検査のプロではないので、検査中に子どもが目を細めたり、あごを引いて上目づかいで回答していたりする様子を見逃している可能性があります。
また、視標が見えていたとしても本人の
応答の問題などで、実際よりも見えて
いないように評価されているケースも
少なくありません。
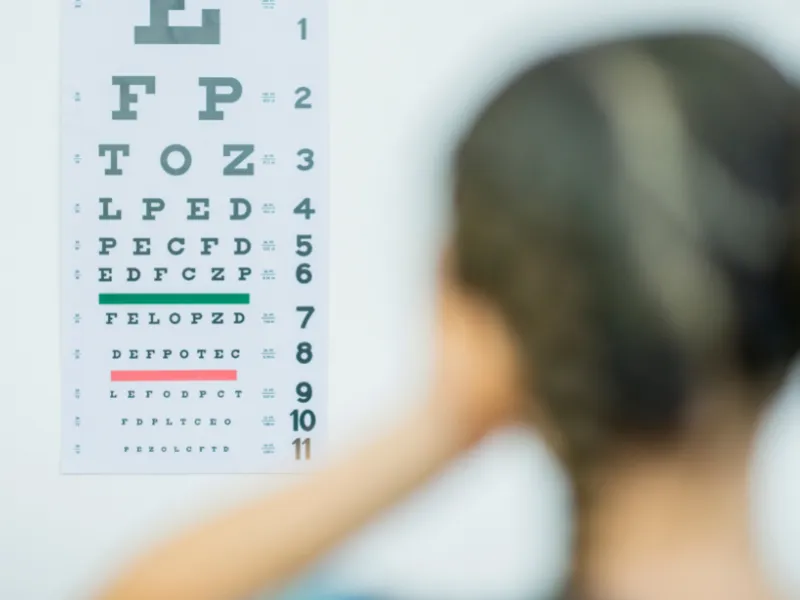
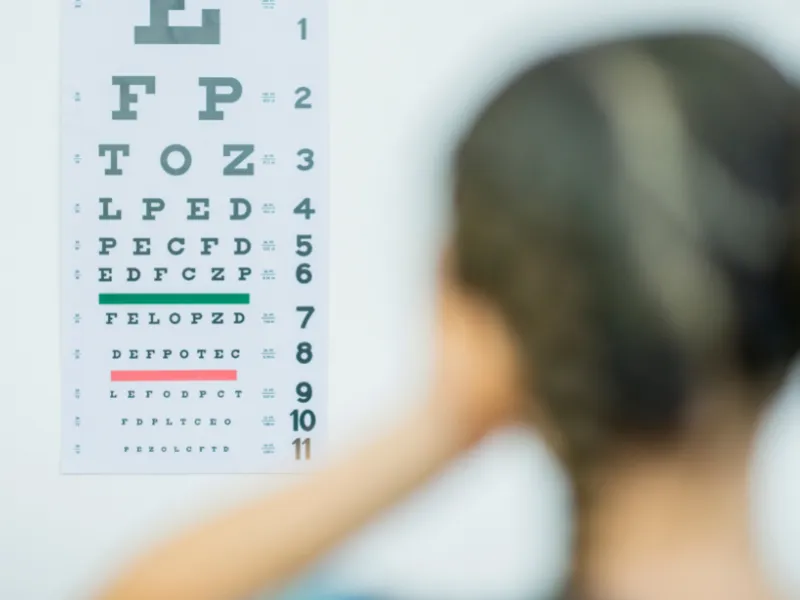
学校検診で引っかかった小児に対する
検査の流れとポイントを解説します。
問診で確認したいことは以下の通りです。
どの判定結果であっても問診は省略せず、
必ず本人・保護者それぞれにしっかりと
行って下さい。
本人に聞くことの一例
保護者に聞くことの一例
本人の受け答えがしっかりしていた
としても、
本人と保護者の問診結果が一致しているかどうか
を必ず確認して下さい。



認識が一致しているほど検査後の説明や眼鏡処方への理解がスムーズになります
問診の結果を意識しつつ、
視力検査を行います。
検査中の
「目を細める様子の有無」は、視力的に眼鏡処方を悩む場合に大きな判断材料
となるため、しっかりと
チェックして下さい。



また、裸眼での両眼視力も同様に、眼鏡処方の判断材料となります
具体的な視力検査の方法や眼鏡処方
度数決定に関しては、こちらの記事
で詳しくまとめています。


「どのくらいの裸眼視力から、
眼鏡処方を検討したらいいのか」と
悩む人も多いかもしれません。
施設ごとの方針による違いや、本人の
自覚など個人差も大きいため明確な
基準はありませんが、一つの目安
として参考にして下さい。
※説明の便宜上、視力の分類は学校検診のA~D判定の視力と対応させています。
特に左右差などもなく、1.0以上の
視力が出ている場合は眼鏡処方の
必要はありません。
保護者には、今後また学校検診で
指摘される・本人が見づらさを
訴えるなど何かあれば早めに
受診するように伝えて下さい。
この視力は眼鏡処方をするかしない
か、悩ましいと感じる人も多い
かもしれません。
判断材料は以下の通りです。
一般的に、黒板の文字を教室の一番
後ろから読み取るために必要な両眼
視力は0.8~0.9以上といわれています。
しかし、両眼視力が0.8以上であっても、
日常的に目を細める様子が見られたり、
本人が見づらさを訴えていたりといった
場合には眼鏡処方を検討して下さい。



また、黒板の文字は学年が上がるごとに小さくなることも考慮し、「次回は眼鏡処方が必要かもしれない」と保護者に伝えておいてもいいでしょう
眼鏡処方を勧めたい視力ですが、本人
や保護者が眼鏡処方に抵抗がある場合
は裸眼で様子を見ることもあります。
その場合は以下の内容を保護者に説明し、
次回以降は眼鏡処方になる可能性が
高いことをしっかりと理解してもらって
下さい。



0.6は一番前の席なら大丈夫ですが、0.3だと厳しいはずです。
C判定にも幅があるので、できる限り保護者を説得し、眼鏡装用へ導いて下さい!
早急に眼鏡が必要な視力です。
このままだと勉強や日常生活にも
支障をきたしてしまうことを説明し、
眼鏡処方を行って下さい。
すでに近視が進んでおり、初めての
眼鏡が強めの度数になってしまう
場合は、弱めの度数からスタートして
段階的に度数を上げていきます。
定期的に眼鏡の作り替えが必要に
なるため、眼鏡の保証期間を含め、
保護者への説明を丁寧に行って下さい。



眼鏡処方へ持っていく話術、堂々とした対応も視能訓練士に必要なスキルです
学校検診でのA~D判定はあくまでも
参考程度にとらえ、どの判定であっても
問診や視力検査をしっかりと行って下さい。
また、たとえ今回は眼鏡処方を見送って
様子を見る場合でも、保護者に対して
近視や眼鏡の可能性についてしっかり
と説明を行うことが大切です。
眼鏡処方を悩む場合の判断材料は、
本人の自覚や日常・検査中に目を
細めていないかなどです。



視力や屈折だけにとらわれず、問診や検査中の様子も注意深くチェックして下さい。
参考
一般社団法人 大阪府眼科医会
「教室における黒板の文字の見え方の検討― 視力が 0.7 以上あると黒板の文字が見えるのか ―」日本視能訓練士協会誌


\ 簡単10秒登録 /

