今の職場に悩んでいたら・・・

\ 簡単10秒登録 /


\ 簡単10秒登録 /


 視能訓練士
視能訓練士すぐ泣き出したり嫌がられたりして、小児の検査がぜんぜん進まない…
小児の視力検査は、弱視の発見や
治療のためにとても大切です。
しかし、小児は検査を嫌がったり
泣いてしまったりと検査協力が
得られないことに加え、集中力が
続かないという特徴があります。
そのため、思うようなに検査ができず、
小児視力検査に自信が持てないという人も
少なくないでしょう。
この記事では、視能訓練士として
多くの小児検査を経験してきた私が、
小児視力検査での悩みに対して、
解決策を紹介します。
小児専門外来に勤務経験のある
視能訓練士が、嫌がる小児の
検査のコツを解説!





視能訓練士歴8年、小児専門外来に勤務経験があり、小児検査ならではの悩みと日々向き合ってきました!
外来の小児視力検査において、
悩みがちな2つの点についての
解決策をまとめました。
視力検査は自覚的検査のため、
検査協力を得ることが不可欠です。
しかし小児の場合、検査を始めること
すらできない場合も多いでしょう。
具体的には、以下のような状態です。



もうすべて投げ出したくなります…
小児が検査を嫌がったり
泣いてしまったりするときは、
不安や恐怖を感じている
可能性があります。
そのため、まずは
検査は怖くない・痛くない
ということを伝えて、安心して
もらうことを意識しましょう。



保護者の協力が不可欠です!
具体例
一緒に検査を受けてもらう
先にレフをのぞいてもらう
先に検眼枠をかけてもらう



調節麻痺剤の点眼を嫌がる場合はいきなり点眼するのではなく、まず本人の手の甲などにつけるといいですよ
また、必要以上に検査を嫌がったり
泣きじゃくっていたりする場合は、
「機嫌が悪い」ことが原因の場合
もあります。
無理に検査を続行せずに、
など、少し時間を置いて
気分転換をさせてみましょう。
小児の集中力が続かないのは
当たり前のことですが、わかって
いてもうまく対応できない
という人もいるでしょう。
小児の集中力には個人差があるため、
同じ年齢でも集中力は異なります。
その日の気分や調子によっても
ばらつくことが多いため
「前回できた検査」が今回もできるとは限りません。
検査の計画を立てる際は、
集中力が続く時間を
予測することが大切です。
症例にとって、
診察に必要な最低限の情報(検査結果)は何か?
を考えて、事前に検査の順番を
組んでおきましょう。



優先順位をつけるということですね!
検査前から準備することに
よって、自分自身も落ち着いて
検査に望めます。
単調な検査にならないように
検査の順番を意識すること
も大切です。



症例にもよりますが、TSTなどの立体視検査を途中で挟むことで、気分転換になる場合もあります
また、集中力やモチベーションを
保つには、
小児が好きなこと、興味があることを声かけや検査に取り入れる
のも効果的です。
検査前に保護者に確認して
おきましょう。
「声かけの例」
「ずーっと見てたら(視標に)〇〇が出てくるかもしれないよ!?」
「(検査ができたら)すごい!〇〇みたいにかっこいいね!」





小児視力検査をスムーズに行うためには、保護者の協力が不可欠です
検査中の声かけはもちろん、
普段の様子や小児が好きなものの
情報を共有してもらうことができれば、
より効率的な検査計画を立てられます。
保護者と接する際には笑顔や話し方を
意識し、信頼してもらえるような
コミュニケーションを心がけて下さい。
診察に直接関わることは、
視能訓練士の立場として話せないこと
もありますが「近視とは?遠視とは?」など
基本的なことはわかりやすい言葉で
説明できるようにしておくといいですね。
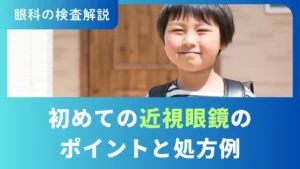
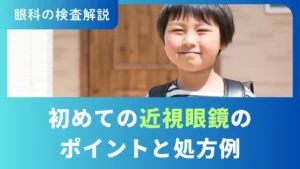


大人の検査とは違い、思うように
いかない小児の視力検査は大変です。
しかし、事前にその症例にとって
しっかりと準備をしておくことで
落ち着いて検査に望めるでしょう。
検査者があせってしまうと、
そのあせりや不安が小児に
伝わってしまうこともあります。
まずは「検査は怖くない」という
ことを伝え、少しでも検査に
興味を持ってもらうことを意識
して下さい。




\ 簡単10秒登録 /

